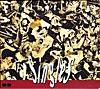中島みゆき「糸」をEから歌うかAから歌うかによって曲調が違う。そもそも中島みゆきの声は、わたしの理想とする無愛想な声だ。愛想が悪いのではなく愛想がないのだ。そこに真実がある。夏目漱石が「草枕」に書いた「不人情」と「非人情」との違いだ。声の表現で重要なのは非人情な自己表現なのだ。
— 渡辺知明 (@WATANABE_tomo) 2019年4月13日
聖人とは、人間の形を持ちながら人間の情を持たぬ存在だ。かれは人間の形を持つがゆえに、人間社会に生きる。しかし、人間の情を持たぬから是非にとらわれない。聖人といえども、一個の人間としては微々たる存在にすぎない。だがかれのみが自然と一体化して、その限りない偉大さをわがものとなし得るのである。
恵施が荘子に議論をふっかけた。
「きみは聖人は情を持たぬというが、人間が情を持たぬことが可能だと考えているのか」
「そのとおり」
「人間は情あってこそ人間といえるのだ。情を持たぬものを、どうして人間といえる」
「天が人間の形をあたえたものを、人間といわずになんといおう」
「人間という以上、情を持たぬというのは矛盾ではないか」
「わたしが情を持たぬといったのは、情にとらわれぬということだ。好悪の念にとらわれて、われとわが身を損なうことなく、いっさいを自然にまかせて、人為的なつけ加えをしないということだ」・・・・・
「聖人に情ありや否や」のテーマは、後の魏晉の時代になると、当時の清談によって再び重要な論題として取り上げられるのであるが、その代表的な議論である王弼(おうひつ)と何晏(かあん)の要旨を参考までに掲げてみよう。
何晏;聖人とは超絶的な人格であって、彼には本来、凡俗のごとき喜怒哀楽の情はない。
王弼;いや違う。聖人も本質的には凡俗と同じだ。聖人にも喜怒哀楽の情はある。ただ彼は凡俗の持たない霊妙な精神のはたらきをもっているので、そのすぐれた精神のはたらきで、外界の事象に接していき、自己の心を喜怒哀楽の情によって乱されることがないだけだ。(三国志巻二八王弼伝注)二人の「聖人無情」に関する議論のうち、王弼の主張が荘子の真意を得ていることは、いうまでもあるまい。
秦失(しんしつ)は老子の訃報に接して弔問に出向いた。かれは霊前で三たび声をあげて泣くという儀礼を行っただけで、そのまま席を立った。そのそっけない態度を見て老子の弟子は秦失をなじった。
「あなたは故人とは旧知の間柄ではありませんか」
「そうだとも」
「親友のあなたがそのような弔い方でいいのでしょうか」
「いいとも。わたしはこれまで、あなた方の先生を尊敬するに足る人物と信じてつき合ってきた。しかしそれはまちがいだったよ。さっき奥の間に通されてみると、老いも若きもまるで自分の肉親をなくしたように泣いていた。あなた方は、それが自然の情だと思っているに違いない。むろん故人は、お悔みをいってくれとはいわなかっただろうし、泣いてくれともいわなかったろう。しかし、結局のところ、かれは無言のうちにそれを求めていたのだ。かれは天の理法から逃れようとし、人間の自然な在り方に背いたのだ。人間の生があたえられたものであることを忘れて生に執着することを、昔の人は天理を逃れようとする罪(頓天の刑)といった。
あなたの先生がこの世に生まれたのは、生まれるべき時にめぐりあわせたからであり、この世を去ったのは、去るべき必然に従ったまでではないか。時のめぐりあわせに安んじ、自然のなりゆきに従っていけば、いっさいのとらわれから解き放たれよう。こういう境地に達した人間を、昔の人は天帝から首枷を解かれた人間(帝の県解)といった。・・・・・」
中島みゆきの「横恋慕」がふと聴きたくなって、でも音源を持っていなかったので、Amazonでベスト「中島みゆき THE BEST」の中古盤をポチッた。「悪女」の次に好きな曲。
— 川井 信之 Nobuyuki Kawai (@Nobuyuki_Kawai) 2019年4月8日
収録曲はいずれも中島のオリジナルアルバムには未収録である。「横恋慕」は『中島みゆき THE BEST』で、「忘れな草をもう一度」は『Singles』でアルバム初収録となった。
2004年に発売されたアルバム『いまのきもち』には、「横恋慕」のセルフカバーバージョンが収録されている。「横恋慕」のセルフカバーバージョンがオリジナルアルバムに収録されるのは初なので、アルバムバージョンとも言えなくはない。
3 横恋慕